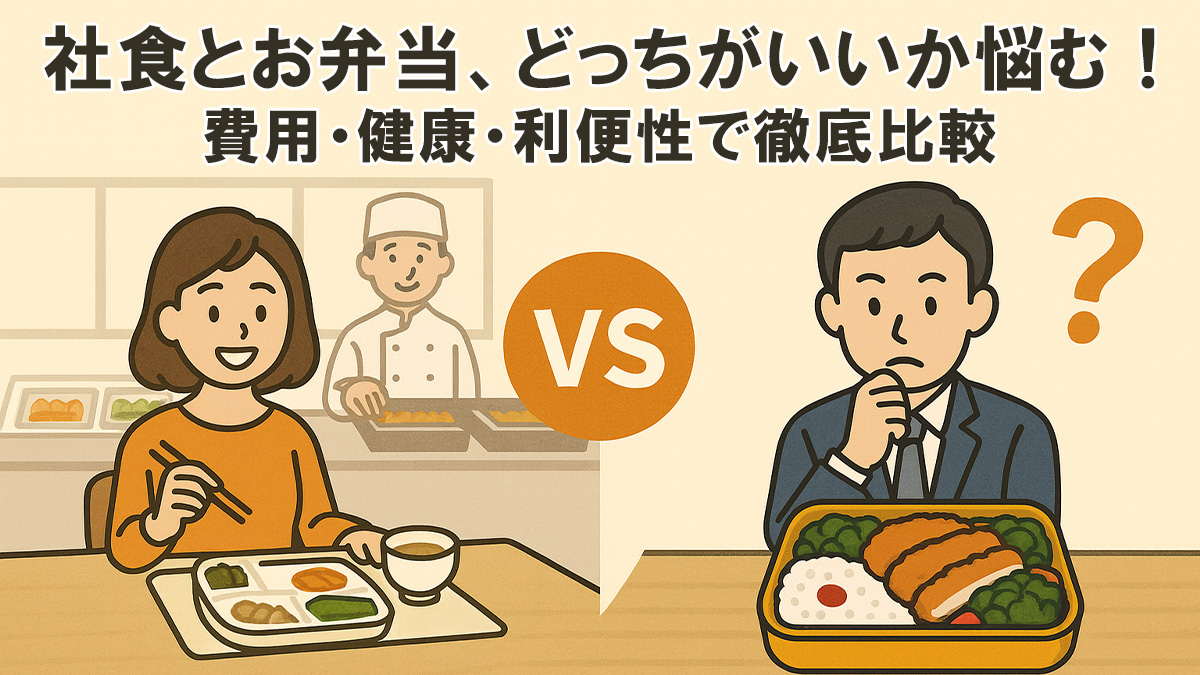昼食は毎日摂るものですから、できるだけ食費やコストを抑えつつ、健康も気にしたいですよね。
働く人・福利厚生を考える企業、どちらも悩みは尽きません。
ここでは、社食(社員食堂)と弁当を「費用」「健康」「利便性」の観点で比較し、あなたの企業・家庭に合ったスタイルを選ぶための指針を提供します。
目次
社食の種類と特徴│導入に向いている企業とは
「社食(社員食堂)」と聞くと、社内に調理場と食堂を備えた常設タイプを思い浮かべる方が多いでしょう。実際には、運営形態によっていくつかの方式があります。
自社運営型(直営)
企業が自社で厨房スタッフを雇い、メニュー開発から調理、提供までを一貫して行います
自社の方針に合わせてメニューを柔軟に決められる一方、人材確保や食材仕入れといった運営負担が大きいため、大企業で導入されることが多いです。
設置型(外部委託)
厨房スペースは自社で用意し、運営を給食会社などの外部業者に委託します。管理栄養士による栄養設計や季節ごとのメニューなど、専門業者のノウハウを活用できます。
初期投資やランニングコストは必要ですが、利用者が多い中規模〜大規模企業で一般的なスタイルです。
出張型(外部委託)
外部事業者が調理済みの料理をオフィスに持ち込んで提供します。
常設の厨房などの初期投資が必要なく、低コストで導入が叶います。
持参した食事を温め直して盛り付けるため、本格的な調理ができないものの、小規模オフィスでも手軽に導入できます。
デリバリー型(外部委託)
従業員向けの弁当をまとめて会社に届けてもらうサービスです。
厨房や大きな食堂スペースが必要なく、小規模オフィスでも導入しやすいスタイルです。
弁当の種類と特徴│自作と購入の違い
自作弁当か、コンビニなどで購入する弁当かによって、かかる費用やメリットが大きく変わります。
自作弁当
材料費を抑えながら、野菜を多く入れたり揚げ物を控えたりと、自分や家族の健康状態に合わせてお弁当を作れます。
一方で、毎朝20〜30分の調理・準備時間が必要になるため手間がかかりやすく、継続するのが難しいという側面もあります。
購入弁当(コンビニ・専門店)
コンビニやスーパー、仕出し弁当屋で販売されている弁当を購入して食べるため、手間をかけず安定したおいしさで食事を取れます。
ただ、揚げ物や炭水化物が多かったり、しっかり味がついていることから塩分・糖分を摂りすぎるなど栄養が偏りやすくなります。
費用で比較|社食と弁当どっちがお得?
社員の負担
社食利用
1食あたり約400〜600円が一般的
※食事補助制度などの補助の有無や規模によって変動します
自作弁当
材料費約300〜400円 + 光熱費・水道代約20~40円 = 目安は320~440円前後
加えて、作成時間に20~30分ほどかかります
購入弁当
600〜800円程度
作り込み方は個人によってばらつきがありますが、社員にとってもっとも費用を抑えやすいのは自作弁当といえます。
作り置きや賞味期限のこまめな確認などの食材を無駄にしない工夫で、費用を抑えやすくなります。
1ヶ月あたりの目安や、より詳しい平均モデルの概算を知りたい方はこちらもご覧ください。
【セカンドキッチンのコラム】
🔗1ヶ月でかかるお弁当の費用はいくら?|社員が悩む出費問題
社食を導入する場合の会社のコスト
自社運営型・設置型
- 初期費用(調理器具、厨房設備、食堂スペースなど)
→数百万円〜数千万円(新規設置・規模による) - 運営コスト
→食材費・調理人件費・光熱費・水道代・施設維持費などがかかります - 従業員への食事補助
→食事補助を導入すると、従業員が支払う金額を抑えられます
社員補助の額 × 利用人数 × 稼働日数 = 月次コスト例
例:200円補助 × 利用者100人 × 20日 = 約40万円/月
出張型・デリバリー型
- 初期費用(調理器具、厨房設備、食堂スペースなど)
→基本不要 - 運営コスト
→1食あたりの金額に食材費・光熱費などが含まれており、従業員個人が支払います。 - 従業員への食事補助
→食事補助を導入すると、従業員が支払う金額を抑えられます。 - 社員補助の額 × 利用人数 × 稼働日数 = 月次コスト
自社運営型と設置型は、厨房設備や器具など調理のために必要な初期費用や運用コストといったランニングコストがかかりやすくなります。
企業側からすると、福利厚生として導入する際には出張型・デリバリー型の社食が費用を抑えやすいと言えるでしょう。
健康&継続性から比較│塩分や脂質に注目
健康は従業員にとっても、企業にとっても重要なポイントです。
従業員の健康維持・増進を経営課題とする「健康経営」という言葉があるように、従業員の健康は生産性や効率にも繋がります。
社食(社員食堂)
管理栄養士がメニューを監修することが多く、栄養バランスが整った食事で、カロリー・過剰な脂質・塩分をコントロールできます。
また、令和3年(2021年)6月1日から食品事業者にはHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務化されており、衛生面でも安心です。
制度について知りたい方は下のリンクからご覧ください。
【厚生労働省HP】(外部に遷移します)
🔗HACCPに沿った衛生管理の制度化について
弁当
自作の弁当は栄養バランスに気を遣うことで、健康的な食事を取りやすくなります。ただ、継続性という観点から見ると、毎日の献立考案と準備で手間がかかります。
購入弁当は味や保存性重視で塩分・脂質が高めのものが多く、野菜不足になりがちです。1日の食塩相当量の目標は、男性7.5g未満/女性6.5g未満(厚生労働省の「日本人の食事摂取基準 2020年版」)とされていますが、それを上回らない工夫が必要です。
また、弁当は夏場の保存や持ち歩きの衛生リスクが課題となります。
利便性で比較│忙しい毎日の効率化
社食(社員食堂)
社外に出る必要がなく、移動に時間を割かずに食事をできます。
昼休みを有効に活用でき、午後の仕事にもスムーズに入りやすいというメリットもあります。
弁当
自作弁当は朝の準備が固定コストとなり、購入弁当は移動や待ち時間が発生します。
この「見えない時間コスト」が、忙しい人にとってはストレスになることもあります。
環境・持続性の観点
環境配慮を重視したごみの削減は、企業の社会的責任を果たすCSR活動にも繋がります。
社食の中でも自社運営や設置型はリユース食器を使えるためごみが少なく、自作弁当も同様です。
一方、出張型やデリバリー型の社食、購入弁当はどうしても包装や使い捨て容器が出てしまう傾向にあります。
あなたの会社におすすめの事例別モデル
社員食堂を導入するときに、どのスタイルが合うかを知るためのモデルを事例別にご紹介します。
- 事例A:20〜50名規模、週数回の出社が中心
→出張型社員食堂では、初期費用をかけずに小ロットから導入できます。低コストかつあたたかい食事で社員の満足度を高めます。 - 事例B:80名程度、毎日出社が多い企業
→ 出張型やデリバリー型の外部委託の社員食堂を導入し、食事補助によって利用率を高め、社員満足度アップを狙えます。 - 事例C:300人以上、大規模・シフト勤務あり
→ 昼夜兼用の自社運営型社員食堂を導入し、夜勤軽食の提供を含めた体制で、働きやすさを後押しします。
優先したいものを決める
企業にとっては、社員食堂は単なる食事提供の場ではなく、従業員の健康維持、満足度向上、社内コミュニケーションの活性化といったたくさんのメリットがあります。
まずは自社の規模や働き方を分析し、必要に応じてアンケートなど従業員の意見を聞くことで、ニーズに合った食事のスタイルを検討してみませんか。
セカンドキッチンでは、初期費用0円で導入できる、1食あたり500円~の出張型社員食堂を提案しています。
30食から承っておりますので、中小企業で社食の導入をお考えの方は、まず一度ご相談ください。